先日、NHK党の立花孝志氏がドバイから帰国後に逮捕されたニュースが大きな話題となりました。
この報道をきっかけに、ドバイが犯罪人引渡条約のない国であることが注目を集めています。
実は世界には、犯罪人引渡条約を結んでいない国が数多く存在するんです。
そうした国々では、海外逃亡が成立してしまう可能性があるって知っていましたか?
今回は、犯罪人引渡条約のない国とある国の違いや、実際に海外逃亡を実行した人たちについて詳しく見ていきたいと思います。
それでは早速本題に入りましょう !
犯罪人引渡条約のない国とある国知ってる?

国際社会では、犯罪者を国境を越えて引き渡すための条約が存在します。
しかし、すべての国がこの条約を結んでいるわけではないんですね。
日本が犯罪人引渡条約を結んでいる国は、2025年時点でアメリカと韓国のわずか2カ国のみです。
これは世界的に見ても実は驚くほど少ない数字なんです。
比較してみると、フランスやイギリスは100か国以上と締結しています。
アメリカでも約70か国と条約を結んでいるんです。
日本がこれほど少ない理由には、いくつかの背景があります。
特に大きな要因とされているのが日本の死刑制度なんですね。
ヨーロッパの多くの国は死刑を廃止しており、死刑が存在する国への犯罪人引渡しを拒否する傾向があるんです。
そのため、日本は「欧州犯罪人引渡条約」にも加盟できていません。
条約がない国との間では、犯罪者を強制的に引き渡す法的義務が存在しないんです。
つまり、アメリカや韓国以外の国で犯罪を犯して日本に逃げ込んだ場合、日本はその犯人を引き渡さなくても良いということになります。
逆に、日本で犯罪を犯した人が条約のない国に逃げた場合も、同じことが言えるわけです。
海外逃亡が成立する場所

では、具体的にどのような国が海外逃亡の成立場所となりやすいのでしょうか?
いくつかの特徴的な国々を見ていきましょう。
犯罪人引渡条約のない国は、逃亡先として選ばれやすいという現実があります。
代表的な国としては、まずレバノンが挙げられますね。
レバノンは自国民を他国に引き渡さないという原則を持っているんです。
そのため、レバノン国籍を持つ人にとっては、非常に安全な逃亡先となります。
また、ドバイを含むアラブ首長国連邦も、多くの国と犯罪人引渡条約を結んでいません。
その他にも、ロシアや中国の一部地域、中東諸国の多くが該当するんですよ。
アフリカ大陸の多くの国々も、日本とは犯罪人引渡条約を結んでいないんですね。
南米では、ブラジルやベネズエラなども条約未締結国として知られています。
このように挙げ始めるとキリがないくらいです。
永住権の取得が容易な国や、入国管理が緩い国も逃亡先として選ばれやすいんですね。
こうした条件が重なると、逃亡犯にとっては「理想的な」隠れ場所となってしまうわけです。
ただし、条約がないからといって必ずしも逃亡が成功するわけではありません。
治安が不安定な国や、法執行が不十分な地域では、別の様々なリスクが存在するからです。
また、政治的な配慮や外交関係の複雑さも逃亡の成否に影響を与えます。
過去に海外逃亡を実行した人たち

実際に海外逃亡を成功させた事例を見ていくと、条約の重要性がよく分かります。
日本人と外国人、それぞれの代表的なケースをご紹介しましょう。
日本人で最も有名な海外逃亡成功例は、カルロス・ゴーンさんです。
ゴーンさんは日本で金融不正の容疑で逮捕されましたが、2019年に保釈中にレバノンへ逃亡しました。
その逃亡方法は映画のようでしたね。
東京の自宅からプライベートジェットでレバノンの首都ベイルートへ渡航したんです。
日本とレバノンの間には犯罪人引渡条約がなく、さらにゴーンさんはレバノン国籍も持っていました。
レバノン政府は日本からの引渡し請求を拒否し、現在もゴーンさんはレバノンに滞在し続けています。
ゴーンさん自身は、日本の司法制度を「人権が無視された差別的なもの」と批判しているんです。
もう一人の日本人の例として、岡本公三さんのケースがあります。
岡本さんは日本赤軍のメンバーで、イスラエルのテルアビブ空港乱射事件に関与しました。
その後レバノンに逃亡し、日本が引渡し請求を行ったものの、レバノン政府はこれを拒否したんですね。
海外の事例では、イタリアの元首相シルビオ・ベルルスコーニさんの名前が挙がります。
ベルルスコーニさんは欧州内での刑事事件の拘束を回避するため、条約の運用における複雑な法的駆け引きを行いました。
一定期間、海外で逮捕を回避することに成功した歴史的な例として知られているんです。
一方で、中国は59の犯罪人引渡条約を締結し、積極的に逃亡犯の逮捕に取り組んでいます。
「天網行動」と呼ばれる国際逃亡犯逮捕活動では、2014年から2020年までに50人以上の逃亡犯を引き渡しているんです。
中国大陸部から18年逃亡していた脱税疑惑の被疑者がペルーから引き渡されたケースは、その代表例ですね。
まとめ!
今回は、犯罪人引渡条約のない国とある国があること、過去に海外逃亡を成立させた代表的な場所や、海外逃亡を実行した人たちについてお伝えしてきました。
NHK党の立花孝志氏のドバイ帰国後の逮捕報道をきっかけに、多くの人が犯罪人引渡条約のない国の存在を知ることになりましたね。
日本がわずか2カ国としか条約を結んでいないという事実は、驚きだったのではないでしょうか?
この問題を考えると、国際社会における法の執行の難しさが浮き彫りになります。
一方で、犯罪者が国境を越えて逃げられる「抜け穴」が存在することも事実なんですね。
興味深いのは、この問題が単なる法律の問題だけでなく、各国の価値観や文化の違いを反映しているという点です。
死刑制度の有無、人権に対する考え方、国家主権の重視度など、様々な要素が絡み合っているんですよ。
ゴーンさんのような高額所得者は、プライベートジェットで逃亡できる経済力を持っています。
しかし一般の人にとっては、海外逃亡は現実的な選択肢ではありませんよね。
結局のところ、犯罪を犯さないことが最も確実な「安全策」なのは間違いないです。
今後、グローバル化が進む中で、国際的な法執行の協力体制がどう発展していくのか注目ですね。
日本も他国との条約締結を増やしていく必要があるのかもしれません。
それでは、ありがとうございました!
“`
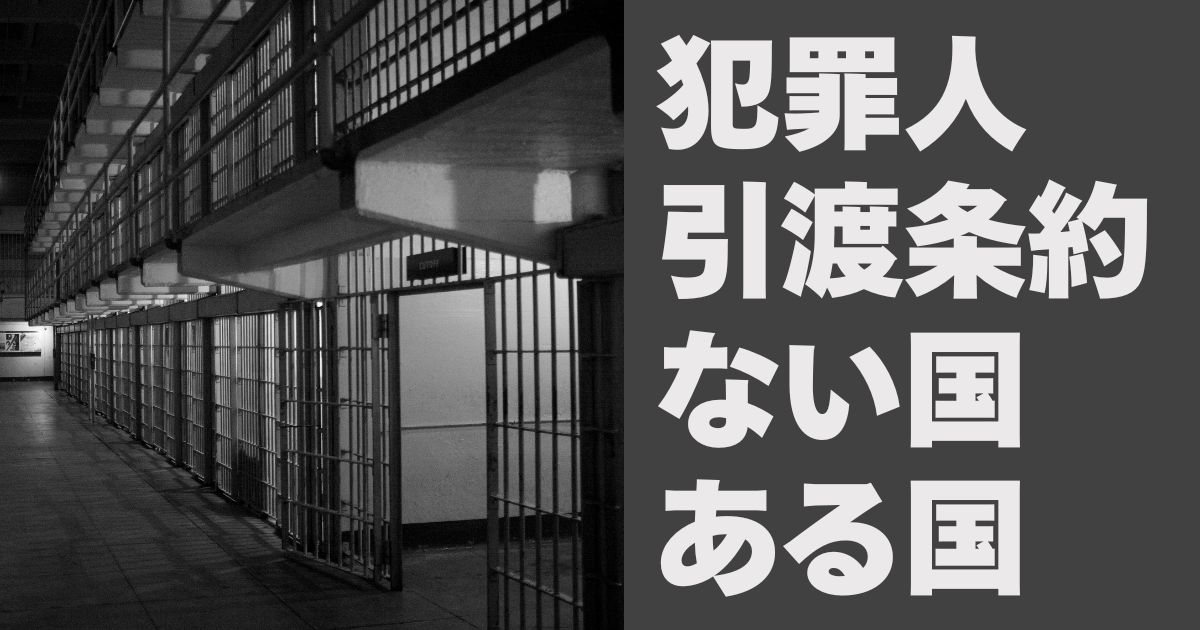
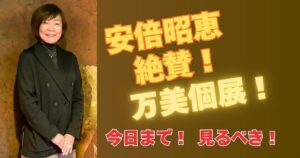


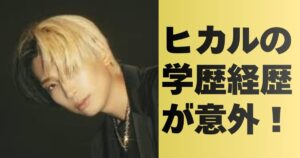
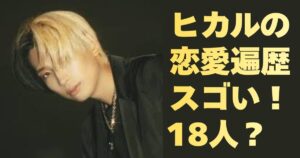



コメント